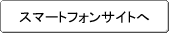|
2022/5/24
|
|
スノケリングやダイビング中の事故 |
|
|
スノーケリングも、水の排出不良により誤飲や溺れ等の事故 ダイビングも事故が報告されています。 水中では体温も陸上の25倍の速さで失われ、体の弱っている機能がさらに悪化して機能不全による身体の不調からくる障害事故等色々あります。 年齢を重ねた体は、悲鳴を上げています、普段から水泳したり、ダイビングしている人は、さほど問題ありませんが、いきなりすると、 体がついて行きません。 何年も潜らず講習修了だけのペーパーダイバーや沖縄観光で久しぶりダイビングなんて、思う人がおりますが、危ないと思ったら金額は 高くても体験ダイビングコースを行った方が安全、 素人としてインストは扱いますから、監視対象になります。 カード保持者でもブランクが開いているダイバーは 体験ダイビングコースをお勧め お互いに思わぬ事故を起こさないために、受けたサービス側も 迷惑します。 お互い事故のないダイビングを楽しむ前に 素潜りでは、脳が酸素欠乏に陥り 意識消失なんてよくあること、10メートルで酸素濃度は1/2に 圧縮20メートルで1/3になります。密度が下がりますから、 水深が増すと、脳に必要な酸素量が減少し ブラックアウトになります。 ダイビングでは、レギュレターを通じて水深に合った空気を供給してくれますが、水深が増し呼吸を自分で止めていると、必然的に酸欠になります。陸上は腹式呼吸で意識しなくても呼吸してますが 水中は、水中環境に慣れないと意識して呼吸しないと、 簡単に酸欠になります。 また、過呼吸もあり、吸っていいのか、吐かないでいいのか 分からない時は、先ず吐くことを行えば、吸入は自動的に付いて来ます吸い過ぎると、逆に呼吸困難パニックになります。 私達が良く講習で教えるのに、呼吸は吐くことを気にしてやれば、吸気は自動的に付いてきますと、水中では吐くことを気にして呼吸して大きくゆっくり呼吸することを教える。 ゆっくり呼吸しながら水深に合った呼吸をすれば、問題ありませんが、急激に潜水し、水圧に合わない呼吸や、他のことに意識集中すると、呼吸を忘れがちになり 簡単に意識消失します、踏ん張って対応していると呼吸停止していることが多く、その間に水中転落して酸素欠乏に至る。 水中環境に慣れていない人は、潜水中に、他の心配事で、耳抜きや、マスク内に入る海水やBC浮力調節不良等で、水深が増し、その結果酸素不足、やめまいや、意識の喪失等で事故に至るケースが、近くで誰かいれば、すぐに引き上げれば助かりますが、発見遅れれば 死亡します。 他にも溺れや、機材の操作ミス、レギュレターのリカバリーミス、 エアー切れ タンクセッティングのバルブの開閉不良による送気圧力不足等 上を向いて呼吸すると、肺に入る空気量が少なくなります(上を向いて呼吸してみてください陸上でも苦しい、下を向けばエアーは必然的に上がってきますから楽になります)まして水の中では心配になり上を向きます、水圧も加わり上から空気を吸うのは呼吸しにくいのです、ましてホースから空気は来ますから、錯覚でエアーが足りないと 勘違い、パニックに、焦って浮上、肺の破裂や、潜水病等考えられますが、ダイバーは必ず、これが駄目なら、この方法と対策のできる人がダイバーなんです。 昔よく言われたのが、インストはどんなことがあっても水中で亡くなってはならない ダイビングを目指す人に不安を与えるからと 潜る前にインストに自分の状況伝えておくと注意して見てくれます。 違う世界に侵入するわけですから、訓練はしておかないと 安全なダイビングは、普段から、練習しておかないと体が対応できません。 ダイバーは、職人の世界です。 これから水の事故は増えます、楽しいはずの旅行が、事故で台無しにならないように 注意しましょう。
|
|
| |